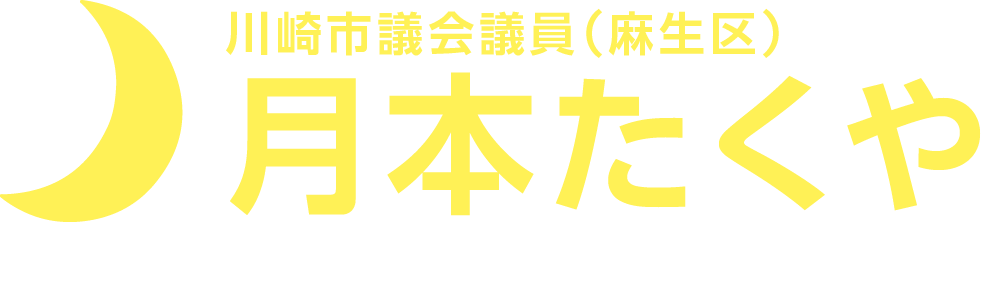昨日、大阪で「地方議員が活用するための自治体行政評価セミナー」に参加しました。
昨日、大阪で「地方議員が活用するための自治体行政評価セミナー」に参加しました。
講師は関西学院大学専門職大学院稲沢克祐教授。
稲沢教授は、社会福祉士、群馬県庁勤務(途中でロンドンに派遣)等を経て、現職で、行政評価論、公会計論、地方財政論を専門にされています。
受講者は私を含め8名の自治体議員で、神奈川県から鎌倉市議が二人参加していました。
「行政評価」という言葉は、慶應義塾大学の上山信一教授が著書で使ったことが始まりとされ、各地で様々な形での行政評価が行われています。
行政計画
行政の計画は、
30年先まで考える基本構想
10年程度の総合計画
2~3年程度の実行計画
ということで、基本構想を最上位計画として、どんどん各論になって来ます。
総合計画には、基本目標・基本政策の下に施策があり、その下に各事務事業が存在します。
例として、
基本政策:誰もが心豊かに健やかに暮らせるようにする。
この目標達成のため、
施策:罹患率を下げる。
この目標達成のため、
基本事務事業:疾病を予防する。疾病を早期に発見する。
この目標達成のため
事務事業:健康増進・生活習慣病予防・感染病予防、健康診断・痴呆の早期発見
という上位政策達成のために、細かい事務事業が存在します。
川崎市では、毎年、施策の評価が行われていますが、自治体によっては、施策と事務事業の両方の評価を行っているところもあります。
新たな総合計画素案の評価の課題
川崎市は、総合計画のない2年の中、来年度開始を目指した総合計画素案が7月に示され、市議会議員への全員説明会の場で質疑を行いました。
ここで私は、施策評価に「市民満足度」の項目が目標指標に導入されると、上位政策である基本計画やポイントとなる年次の目標が明確でなければ、ポピュリズム的な、いわばバラマキ事業を進めると評価を上げる要素になりかねないと言う点を指摘しています。
施策評価と事務事業評価
今回のセミナーを通じ、他都市で行っているような施策全体の評価につながる、施策の中にある事務事業の一つ一つの両方の評価を行うことが大切であると感じました。
川崎市の場合は、施策評価が、事業を行ったかどうかの結果論と一部事業の参考指標を積み上げ、自動的に達成度を示している評価に過ぎず、課題があっても目標達成できたという評価になっています。
セミナーでは、ロジカルな説明と稲沢教授が携わったいくつかの都市の実務事例を通じた講義が進められましたが、川崎市の施策評価はほぼ「達成できた」という評価ですが、事例にあった事業評価では、課題点の抽出と報告でまとめられています。
いわば、課題抽出表になっていて、決算時にその中身を議会に知らせることにより、次年度(決算は平成26年度とすれば、平成27年9月なので、平成28年度)の予算要求になります。
ここで、川崎市の現状のように「できた」「できない」の事業評価の積み上げによる施策評価では、単年度でできなかったものについて突発的な事情の説明を行うに過ぎず、評価は責任論になり、評価はいいか悪いかにつながるだけになります。
しかし、ここで紹介された事例では、妥当性、効率性、有効性の観点から評価を行います。
妥当性は、その事業をすることが必要なのかどうか。
効率性は、その事業の活動結果が適切なのかどうか。
有効性は、その事業を行った成果が適切なのかどうか。
妥当性が低ければ、事業そのものの見直し、有効性が低ければ、事業の進め方の見直しのポイントが明らかになります。
このような事務事業の評価手法を進めることが、施策評価を適切に行う客観的なものにつながります。
そこではじめて市民満足度が一つの指標として活用できるというものです。
そう言った意味で、行政側は事業を徹底的に検証した結果を議会に報告し、議会は課題に対する改善策を提案する場所になります。
次回の定例会では総合計画が上程されるため、評価のチェックシートがどのようなものになっていくかまで踏み込んだ議論を行い、審査していきたいと思います。