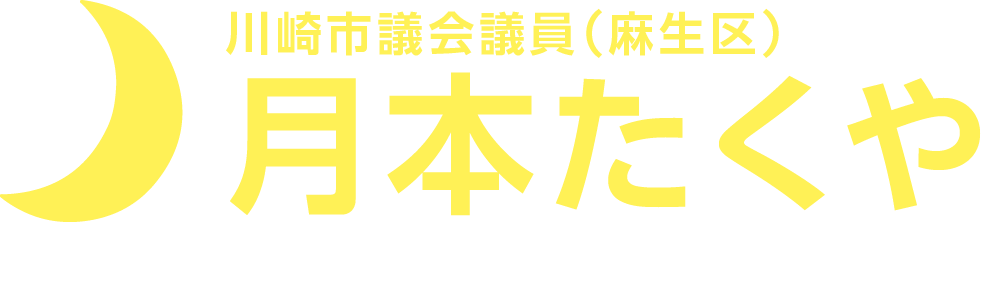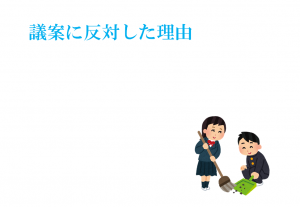 中学校給食の南部給食センター整備事業の契約の締結に関する議案に対する私の考え方についてご説明致します。
中学校給食の南部給食センター整備事業の契約の締結に関する議案に対する私の考え方についてご説明致します。
今回の議案は、中学校給食がセンター方式で進められる上で、南部・中部・北部の3センターの第一弾として南部給食センター設置に関する議案です。
総務委員会で異例の4日間の審議が進められた後、本会議では、附帯決議を付けての賛成多数(反対は私のみ)で可決されました。
附帯決議というのは、賛成するけれど、条件を付すものですが、「決議」ですので、拘束力はそれほど強くないと言う点は否めません。
降って湧いて来た「食育」
どこから降って来たのか、突然「食育」と言う言葉を使っています。
川崎市が昨年定めた「川崎市立中学校完全給食実施方針」では、
「○教科や特別活動等における学校給食と関連させた食育、
○給食の準備、片付け等の共同作業や同じ食事を一緒に食べる「共食」による食育
○小学校からの継続的かつ計画的な食育
○地場産物等の給食への活用による食育」
と示されています。
今回の議案研究の際に、食育の内容を調査したところ、すでに実施している他の自治体における成果の分析、効果目標や具体的な成果指標など、給食による食育についてこれまで特に分析がされていません。そのため、今回のセンター建設に合わせ、食育の効果について方向性が見えません。
また、今回の食育についても抽象的な表現ばかりで、正当性をすり替えられ、川崎市にとって必要な本当の食育のあり方について、具体的なものが示されていません。
大前提の議論はどこへ・・・
そもそも中学校給食は、「子どもたちに温かくて、人のぬくもりのある、顔の見える食事の提供」ということが「大前提」であると、私は思います。
しかし、平成29年度実施という時期の確定を第一義としているため、ここで実施できるのは自校方式、親子方式、センター方式のうち、センター方式でしかないわけです。
言わば、目的は、先ほどの「大前提」であるにも関わらず、事業ありきになり、手段が目的化していると言えます。
自校方式
自校方式は、その名のとおり、中学校に給食室を設置します。
これは、まさに、先ほど掲げた「大前提」に合致する方式で、市立小学校で実施している方式です。
事業費用の市の試算としては30年で760億円。
親子方式
親子方式は、給食室のある学校で作って、近くの学校に届ける方式。ゆえに給食室を設置できる学校には設置します。
これは、顔の見える食事とは言い切れない部分もありますが、自校の学校もあれば、近くの学校に給食室があるという面があり、どうしても設置できるスペースのない学校も多々ありますので、自校方式で実施不可能なケースに対応できる手段でもあります。
事業費用の市の試算としては、30年で750億円から850億円。
センター方式
センター方式は、今回の議案で上がっている方式で、市内に3つの給食センターを設置し、そこから給食を運ぶというもの。
温かい食事の提供という点はクリアできると言っていますが、幸区の南部給食センターから宮前区の一部の学校に届けられるということは給食を作ってから生徒が食すまでに望まれる2時間以内というのには厳しいものがあり、衛生面に不安を覚えます。
さらに、顔が見えないと言う点では、「大前提」からは離れます。
事業費用の市の試算としては30年で640億円(今回の議案である南部給食センターは15年で154億円)。
給食費は食材費
これらの事業費用の試算に、生徒側負担となる給食費は入っていません。
すなわち、センター建設も調理や運搬もすべて税負担です。
と言うのも、給食費は、法律で食材費のみしか取れないことになっています。
すると、事業費用はそのまま税負担になるわけです。
知らないうちに子どもたちに負担を押し付ける
30年間の事業と考えると、この640億円を食べた子どもたちが負担をしていくということになりますが、それを知っている方はどれだけいるでしょうか?
給食に賛成か反対かになっていて、中身についてどれだけ知られているでしょうか?
確かに、自校方式ではすべての学校に設置するのは難しいという現実はあります。しかし、親子方式との組み合わせも含め、顔の見える給食の実現は難しいものなのでしょうか?
しかも、費用で、30年間で120億円の違い、年間4億円の違いと考えた場合に、センター方式を進めることがいいのでしょうか?
「厳しい財政状況」というフレーズは常に行政側でも議会側でも出る言葉で、限られた財源の中で市政運営を進めて行かなければいけないと言う割に、簡単に大規模な事業を進めようとしています。
そもそも誰のための給食なのか?
私は育ち盛りの中学生のためでなければいけないと思います。
しかし、今回の議案からはそうは受け止められません。
7月に主権者教育の質疑の中で、ライフステージ教育をしているかどうかの質問をしました。
ライフステージ教育は、人生のステップでどのように将来目標を形成していくか、あるいは計画をしていくかということです。
「給食○×」を問うなら、この点を生徒たちにも給食センター設置を含め、ランニングコストが将来にどのように影響するかを含め、意見を聞くべきと思います。
現に、市が実施したアンケートによると、家から持参するお弁当がいいと答える生徒の方が多い結果でしたので、食べた分を自分たちが税負担していくということも知る必要があります。
生徒たちだけでなく、この話を多くの大人が知らない現実からすると、行政の周知不足、厳しく言えば、市長が都合の悪い話を市民に伝えていないと指摘できます。
平成29年度完全実施という時期だけが先行した影響が今後どのように出てくるかが心配です。
昨年の議会の補正予算で債務負担行為(いわば、15年ローンのようなもの)として給食導入に向けた予算に同意はしました。
しかし、今回の議会は、同時に平成26年度決算議案の審査も行いましたが、予算に対し、決算における扶助費の増の幅が大きいこと、すなわち、今の市政を続けていると予測を超えて負担が増大していく可能性が出て来ました。
すると、昨年の状況よりも悪化することが見込まれる結果になっています。
さらには、給食により昼休み時間が長くなるという影響で、授業時間の変更や部活動の時間減少の可能性については学校によって対応が異なるということで、その影響も心配されます。
よって、給食の内容、「大前提」に合致していないということ、将来負担が重なるということを踏まえ、市民が知る機会を提供せず、市民に将来的な負担を知らせる行政の義務を怠っているということを指摘し、今回の議案には反対しました。